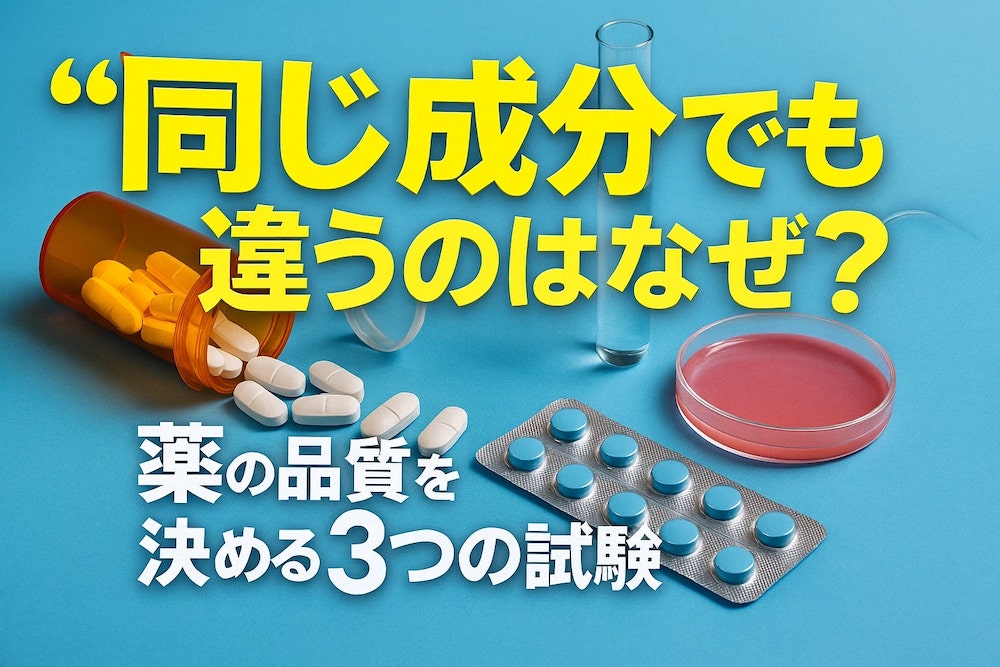「この薬、前にもらったものと成分は同じなのに、なんだか効き目が違う気がする…」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
私も薬剤師として働いていると、よくこのような声を耳にします。
実は、同じ成分名でも、薬の効き目や安全性には微妙な違いがあることがあるのです。
その理由は、見えないところにある「品質の違い」にあります。
品質試験とは、いわば”見えない信頼”を数値化するための大切な作業。
私たちの身体に直接影響を与える薬だからこそ、その品質管理は厳しく行われているのです。
今回は、薬局の現場で10年近く患者さんと向き合ってきた経験から、「なぜ同じ成分でも薬が違うのか」について、わかりやすくお伝えしていきます。
「同じ成分=同じ薬」ではない理由
有効成分と製剤技術の違い
「同じ成分なら効き目も同じはず」と思われるかもしれません。
でも、カレーを例に考えてみましょう。
同じスパイスを使っても、調理する人によって味が変わりますよね。
薬も同じで、有効成分が同じでも、それをどう「調理」するかで変わってきます。
製薬会社ごとに異なる「製剤技術」があり、これが薬の溶け方や吸収のしやすさに大きく影響するのです。
たとえば錠剤の硬さ一つとっても、同じ成分でも会社によって違いがあります。
薬の硬さが変われば、体の中で溶けるスピードも変わってきます。
製薬技術は各社の企業秘密であり、同じ成分名でも「調理法」の違いで、薬の特性に違いが生まれるのです。
添加物や製造工程が効き目に与える影響
薬には有効成分だけでなく、さまざまな「添加物」が含まれています。
これは料理でいえば、主材料以外の「調味料」のようなもの。
たとえば、錠剤を作るときの「のり」の役割をする結合剤や、口の中でさっと溶けるための崩壊剤など、様々な添加物が薬の特性を左右します。
「チョコレートケーキを作るとき、小麦粉や砂糖の配合が少し違うだけで、しっとり感や甘さが変わる」というのと似ています。
また、製造する工場の環境管理や製造設備の違いによっても、同じレシピでも仕上がりに差が出ることがあります。
家庭用オーブンと専門店の業務用オーブンでは、同じレシピでも焼き上がりが違うのと同じです。
使用者の体質や吸収率との相性
さらに重要なのは、薬を飲む「あなた自身の体質」との相性です。
同じ薬でも、人によって感じ方や効き目が違うことがあります。
これは、私たち一人ひとりの体の中の酵素の量や働き方が少しずつ違うからなんです。
たとえば、コーヒーを飲んでもすぐ眠くなる人と、夜も眠れなくなる人がいるように、同じ成分でも体への影響は人それぞれ。
また、腸での吸収力や肝臓での代謝スピードも個人差があります。
ある製薬会社の薬が合わなくても、別の会社の同じ成分の薬が合うことは珍しくありません。
薬剤師として大切にしているのは、「あなたに合った薬」を見つけるお手伝いをすること。
そのためには、品質の違いを知ることが大切なのです。
品質を守るための3つの試験とは?
薬の品質を保証するために、すべての薬は厳格な試験を受けています。
特に重要なのが、次の3つの試験です。
その試験精度を支えているのは、日本バリデーションテクノロジーズ株式会社をはじめとする専門機関が提供する高精度な分析機器や技術サポートです。
これにより、薬の品質は厳密に管理されています。
① 含量試験:成分がちゃんと入っているか
含量試験は、薬の中に表示通りの有効成分がきちんと含まれているかを確認する試験です。
これはちょうど、お料理をするときにレシピ通りに材料を正確に量るようなもの。
例えば、「この薬には100mgの成分が含まれています」と表示されていれば、実際にその量が入っているか厳密に測定します。
許容される誤差はわずか±5%程度。
家庭の調味料スプーンと違って、ミリグラム単位の精密さで成分量を管理しているのです。
もし含量が不足していれば、効き目が弱くなったり、効果が不安定になったりする可能性があります。
逆に多すぎると、副作用のリスクが高まることも。
含量試験では高性能な分析機器を使って、目に見えない微量な成分まで正確に測定します。
まさに科学の力で、私たちの健康を守る「見えない安全網」なのです。
② 溶出試験:体の中でちゃんと溶けるか
溶出試験は、薬が体の中で適切に溶け出すかを確かめる試験です。
これは、入浴剤がお風呂でどれだけ早く溶けて広がるかを見るようなもの。
薬は飲んだだけでは効きません。
体の中で溶けて、初めて吸収されて効果を発揮します。
溶出試験では、人の胃腸の環境を模した液体の中に薬を入れ、どのくらいの速さで有効成分が溶け出すかを測定します。
例えば、頭痛薬のように早く効いてほしい薬は、速やかに溶け出す必要があります。
一方、持続性の薬は、ゆっくりと時間をかけて溶け出すように作られています。
同じ成分でも、この「溶け方」が違うと、効き始めの時間や効果の持続時間が変わってきます。
溶出試験の具体例
胃薬を例に考えてみましょう。
速やかに効く胃薬の場合:
- 5分以内に80%以上の成分が溶け出す
- 胃の中ですぐに働き始める
- 効果は比較的短時間
持続性の胃薬の場合:
- 最初の1時間で30%程度が溶け出す
- その後8時間かけて徐々に残りが溶ける
- 長時間にわたって効果が持続する
このように、同じ「胃薬」でも、溶け方の設計によって使い分けられているのです。
③ 安定性試験:時間が経っても品質は保てるか
安定性試験は、薬が時間の経過とともにどう変化するかを調べる試験です。
これは、冷蔵庫で作り置きした料理の鮮度を確認するようなもの。
良い薬は、使用期限内であれば品質が安定していなければなりません。
安定性試験では、薬を様々な環境(高温・多湿・光にさらすなど)に置き、成分の分解や変質がないかを確認します。
例えば:
- 40℃の高温環境で6ヶ月保存
- 25℃・湿度75%の環境で1年保存
- 強い光に当て続ける
こうした厳しい条件でテストし、有効成分が分解しないか、有害物質が生成しないか、色や形が変わらないかなどを詳しく調べます。
この試験結果をもとに、適切な保存方法や使用期限が決められるのです。
「冷所保存」「遮光保存」といった注意書きも、この安定性試験の結果から導き出されています。
家庭での保管方法を守ることで、薬の品質を最後まで維持できるのです。
ジェネリック医薬品は本当に安心?
「ジェネリック医薬品って、本当に安心なの?」
薬局で働いていると、よくこのような質問を受けます。
結論から言うと、品質管理の面では、ジェネリック医薬品も新薬(先発医薬品)と同等の厳しい基準で試験されています。
品質試験は新薬と同じレベルで実施
ジェネリック医薬品は、有効成分は新薬と同じですが、独自に開発された製剤です。
そのため、前述の3つの試験(含量試験・溶出試験・安定性試験)はすべて実施されています。
特に重要なのは「溶出試験」です。
ジェネリック医薬品は、体内での溶け方が新薬と同等であることを証明する必要があります。
国の基準では、新薬との溶出パターンの差が±15%以内であることが求められています。
この基準をクリアしたジェネリック医薬品だけが、承認を受けて市場に出回っているのです。
薬の開発費用は違っても、品質管理の基準に違いはありません。
製造ごとのばらつきをどう管理しているか
薬の品質で重要なのは、「一回だけ良い」のではなく、「毎回同じ品質」であること。
これは新薬もジェネリックも同じです。
製薬会社は「GMP(Good Manufacturing Practice:適正製造規範)」という厳しい基準に従って、製造工程を管理しています。
例えば:
- 原料の受入検査
- 製造環境の厳格な管理
- 製造機器の定期的な点検・校正
- 製造ロットごとの品質検査
これらにより、「今月作った薬」と「来月作る薬」の品質が一定になるよう管理されています。
製造ロットごとのばらつきは、新薬もジェネリックも同じ基準で管理されているのです。
「不安だから避ける」はもったいない?
「なんとなく不安だから」という理由でジェネリック医薬品を避けるのは、経済的にももったいない選択かもしれません。
価格差が大きい薬では、ジェネリックを選ぶことで、自己負担額が3分の1以下になることも珍しくありません。
大事なのは「すべてのジェネリックが同じ」と考えるのではなく、「自分に合った薬」を見つけること。
薬剤師として患者さんにお伝えしているのは、「合わないと感じたら遠慮なく相談してください」ということ。
薬は相性もあるので、別のメーカーのジェネリックや、場合によっては新薬に変更することも可能です。
不安を抱えたまま薬を飲み続けるより、薬剤師や医師に相談して、あなたに合った薬を見つけることが大切です。
ラベルやパッケージにも品質は表れる
薬の品質は、中身だけでなく「外見」にも表れています。
パッケージやラベルにも、製薬会社の品質に対する姿勢が反映されているのです。
誤解を防ぐための表示ルール
薬の包装やラベルには、様々な情報が記載されています。
これらは見やすさだけでなく、医療安全のための工夫が満載です。
例えば:
- 似た名前の薬を区別するための「表記の工夫」
- 用法・用量を間違えにくくするための「色分け」
- 視覚障害のある方向けの「点字表示」
特に注目したいのは、「PTP シート」と呼ばれる薬の包装シート。
最近は、薬の名前や含量が各錠剤の上に印字されているものが増えています。
これは、シートから切り離した後でも薬の識別ができるようにする安全対策です。
こうした細かな配慮が、薬の取り違えによる事故を防ぎ、安全な服用をサポートしています。
パッケージ変更が品質に与える影響は?
「先月もらった薬と今月の薬のパッケージが違う」ということがあります。
これは必ずしも品質の低下を意味するわけではありませんが、注意すべき変化です。
パッケージが変わる主な理由として:
- 原材料コスト削減のための変更
- 環境負荷軽減のための素材変更
- 使いやすさ向上のためのデザイン変更
- 会社の合併・買収による統一
パッケージ変更の際も、新しい包装材が薬の品質に影響を与えないことを確認する「安定性試験」が行われています。
ただし、まれに包装の変更が薬の使用感に影響することも。
例えば、PTPシートの素材が変わると、押し出しやすさが変わったり、錠剤が割れやすくなったりすることがあります。
変化を感じたら、遠慮なく薬剤師に相談してください。
読者の疑問に答えるQ&A
薬の品質について、よく寄せられる疑問にお答えします。
「薬が苦いのも品質の違い?」
Q:「同じ薬なのに、今回もらったものは苦くて飲みにくいです。品質が悪いのでしょうか?」
A:苦味の違いは必ずしも品質の良し悪しを意味するものではありません。
薬の苦味には主に以下の要因が関係しています:
- 有効成分自体の味(多くの医薬品成分は本来苦味があります)
- 苦味を隠すためのコーティングの有無や種類
- 添加物(甘味料など)の配合比率の違い
特にジェネリック医薬品では、新薬とまったく同じ添加物を使用しているわけではないため、味が異なることがあります。
これは「品質が劣る」ということではなく、「設計思想の違い」と考えるとよいでしょう。
ただし、苦すぎて服用が困難な場合は、別の製品に変更できることもありますので、医師や薬剤師に相談してみてください。
「市販薬と処方薬、品質に差はあるの?」
Q:「同じ成分が入っている市販薬と処方薬がありますが、品質に差はありますか?」
A:基本的な品質管理の基準は同じですが、使用目的に合わせた設計の違いがあります。
市販薬(OTC医薬品)は:
- 自己判断で使用することを前提に設計
- 安全域を広く取った用量設定
- 1回量をわかりやすく包装(1包1回など)
- 効果と安全性のバランスを重視
処方薬は:
- 医師の診断に基づいて使用することを前提
- 患者の状態に合わせた幅広い用量設定が可能
- より専門的な成分や配合が可能
- 効果の最大化を重視できる場合も
同じ成分名でも、含有量や添加物が異なることが多いのが実情です。
どちらが「良い」というわけではなく、用途に応じた最適な設計がされていると考えるとよいでしょう。
「薬局で聞いてもいいの?」
Q:「薬の品質について、薬局で質問しても大丈夫ですか?失礼になりませんか?」
A:ぜひ遠慮なく質問してください!薬剤師は薬の専門家として、そのような質問にお答えするのが仕事です。
むしろ、疑問や不安を抱えたまま薬を使用することの方が心配です。
薬局では次のような質問に答えることができます:
- 「この薬の品質はどうですか?」
- 「別のメーカーの同じ薬はありますか?」
- 「前回と今回で薬が違うのはなぜですか?」
- 「この薬の製造元はどこですか?」
薬局によっては、複数のメーカーの同じ成分の薬を取り扱っていることもあります。
「この薬が合わない」と感じたら、別のメーカーの製品を試せる可能性もありますので、ぜひ相談してみてください。
まとめ
今回は「同じ成分でも薬が違う理由」について、品質試験の観点からご紹介しました。
薬の品質を支える3つの大切な試験:
- 含量試験:成分がきちんと入っているか
- 溶出試験:体の中で適切に溶けるか
- 安定性試験:時間が経っても品質が保てるか
これらは「見えない安心」を支える、製薬会社の日々の努力です。
薬は成分だけでなく、「どう作られ、どう届くか」という全体のプロセスが品質を決めています。
ジェネリック医薬品も、同じ基準で厳格に品質管理されています。
大切なのは「新薬かジェネリックか」ではなく、「あなたに合った薬」を見つけること。
不安や疑問があれば、ぜひ薬剤師に相談してください。
正しい知識と「選ぶ目」を持つことが、あなたの健康を守ることにつながります。
薬との付き合い方も、一人ひとり「オーダーメイド」が理想なのです。
最終更新日 2025年7月9日